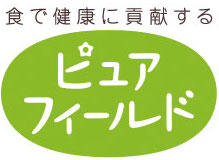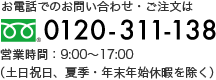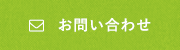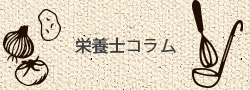【東洋医学×栄養学】夏の疲れは“睡眠の質”に出る!食事でできる快眠サポート法

暑さが厳しい8月は、気温だけでなく“睡眠の質の低下”に悩む方も多い時期です。
「夜に何度も目が覚める」「眠りが浅くて疲れが取れない」…そんな不調が出てきたら、それは夏バテによる自律神経の乱れや、胃腸の疲れ、栄養不足が原因かもしれません。
今回のコラムでは、東洋医学と現代栄養学の視点から、睡眠の質を高める食事方法を解説します。冷房疲れや夏のだるさで眠れない方、自然な方法で不眠を改善したい方に役立つ内容です。
目次
夏に眠れなくなる理由とは?東洋医学と栄養学で読み解く
東洋医学では、夏は「心(しん)」が高ぶりやすい季節とされており、“心火(しんか)”と呼ばれる熱がこもることで、不眠や夢の多い睡眠になると考えられています。また、冷たい飲食物やエアコンによる「冷え」が、消化器系(=「脾」)を弱らせ、睡眠にも悪影響を与えます。
一方、栄養学的にも、夏の睡眠不調は以下のような原因が関係しています。
・食欲低下による栄養不足(特にたんぱく質、ビタミンB群)
・夜間の深部体温が下がりにくく、寝つきが悪くなる
・自律神経の乱れ(副交感神経が優位になりにくい)
つまり、夏の不眠を改善するには「食事を通じて心身の熱を鎮め、必要な栄養をしっかり補うこと」がポイントになります。
睡眠の質を上げるために食べたい“快眠食材”
1. 心を鎮める「安神作用」のある食材(東洋医学的アプローチ)
・百合根:緊張や不安を和らげ、心を落ち着ける。おかゆやスープにおすすめ。
・蓮の実(れんし):イライラや不安を抑え、不眠に良いとされる食材。
・菊花茶・ジャスミン茶:香りで気分をリラックスさせ、心身を落ち着ける。
2. “腎”を養ってぐっすり眠れる体に(深い睡眠に必要なエネルギーを補う)
・黒ごま・黒豆・きくらげ:腎の精(エネルギー)を補い、睡眠中の回復力をアップ。
・脂ののった魚(鮭、いわし、うなぎなど):腎精を補い、疲労回復・睡眠の質向上に役立つ。
3. 栄養学的に見た“快眠を助ける栄養素”
| 栄養素 | 効果 | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料 | 豆腐、納豆、卵、バナナ |
| ビタミンB6 | トリプトファンの代謝を助ける | 赤身の魚、にんにく、バナナ |
| マグネシウム | 神経の興奮を抑える | 海藻類、ナッツ、玄米 |
| GABA | リラックスを促す | 発芽玄米、トマト、じゃがいも |
▶ おすすめの快眠ごはん:「納豆ごはん+鮭の塩焼き+味噌汁」
→ トリプトファン+ビタミンB6+炭水化物の理想的な組み合わせです。
睡眠の質を下げない「食べ方」のコツも大切!
・夕食は就寝の3時間前までに
・冷たいものは控え、温かい汁物を添える
・刺激物(アルコール、辛いもの、カフェイン)は夜は控える
・夜の間食は控えめに。食べるなら、バナナや温かい豆乳などがおすすめ
また、朝に光を浴びること・日中に体を動かすことも、睡眠の質向上に効果的です。朝の散歩やベランダでの深呼吸だけでも、メラトニンの分泌が整いやすくなります。
まとめ:“夏の不眠”は食事でやさしく整える
8月の暑さや冷房によるダメージは、見えないところで心身のバランスを崩しています。とくに、睡眠の質の低下は「夏バテ」や「免疫力低下」「メンタルの不調」などにもつながりかねません。
東洋医学の「心・腎」のケアと、栄養学的アプローチを合わせた食事法を日々の生活に取り入れることで、自然な眠りを取り戻すことができます。
眠れないときほど、薬やサプリに頼る前に「食事」を見直してみましょう。
小さな積み重ねが、きっと快適な夏の夜へと導いてくれます。
著者プロフィール
椙山女学園大学卒業後、食品原料商社にて様々な食品原料の開発に携わる。現在は、フリーランス管理栄養士として年間500人以上に栄養指導、食品添加物セミナー、企業のコラムなどを執筆。また、マクロビ・薬膳・自然療法・望診を学び、西洋・東洋の面から見た、病気にならない体づくりを研究中。
《保有資格》
管理栄養士 / 管理薬膳師 / 上級望診指導士