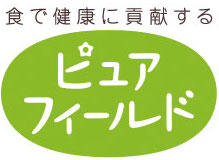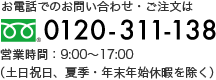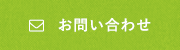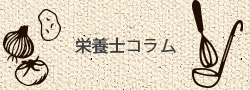熱中症対策に!体の熱を冷ます食材と水分補給の工夫

観測史上初めて6月に梅雨明けする地域もあるように、今年の夏も早々に熱くなっていますね。強い日差しと高温多湿な気候は、私たちの体に大きな負担をかけます。中でも注意が必要なのが「熱中症」です。熱中症は、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節がうまくできなくなることで起こります。
栄養学では熱中症を防ぐために、「水分補給」や「電解質(ミネラル)」のバランスが大切だとされています。一方、東洋医学でも夏は「心(しん)」の季節とされ、体に熱がこもりやすく、発汗によって「気(エネルギー)」や「津液(体の潤い)」が消耗されやすいと考えられています。
今回は、東洋医学と栄養学の両方の観点から、夏を快適に乗り切る食養生のポイントをご紹介します。
東洋医学から見た夏の過ごし方
東洋医学では、夏は「陽」が最も盛んな季節で、「熱邪(ねつじゃ)」が体に入りやすいとされています。「熱邪」は体の内側に熱をこもらせ、のぼせ・イライラ・口の渇き・不眠・動悸などの不調を招く原因になります。また、汗をかきすぎることで「津液」が失われ、「陰虚(いんきょ)」と呼ばれる状態に陥ることもあります。これは体の潤いが不足し、喉や皮膚の乾燥、倦怠感などにつながります。
このような状態を防ぐには、「清熱(体の熱を冷ます)」「生津(体に潤いを与える)」「補気(気を補う)」という三つの視点から食事を整えることが大切です。
体の熱を冷ます食材を取りいれる
体にこもった熱を冷ますには、東洋医学で「寒性」「涼性」とされる食材を意識的に取り入れることが効果的です。以下のような食材が挙げられます。
スイカ:代表的な清熱・生津食材。体の熱を冷まし、水分を補給する効果があります。
きゅうり:熱を取り、利尿作用もあるため、むくみが気になる人にもおすすめです。
トマト:涼性であり、体の潤いを補う働きもあります。リコピンなど抗酸化成分も豊富。
緑豆:体にこもった熱を下げ、解毒作用もあるとされています。
ゴーヤ:苦味に分類され、苦味は「心」を冷ます作用があり、イライラや不眠にも効果的です。
上記の食材は、体が冷えている人、冷えやすい人、胃腸が弱い人は少し注意が必要です。
「冷たいまま」「生」で大量に摂るのではなく、温かいスープや炒め物など、加熱調理で取りいれることがポイントです。体を冷ましつつ、冷えすぎることを防ぎ、胃腸への負担を和らげることができます。
栄養学的な「水分補給」の工夫
熱中症予防の基本は、こまめな水分補給です。人間の体は、体温が上がると汗をかき、体を冷やそうとしますが、この時水分と一緒にナトリウム(塩分)やカリウムなどのミネラルの失われます。そのため、水だけでなく、塩分とミネラルも一緒に補給することが大切です。
市販の経口補水液やスポーツドリンクも選択しの一つですが、日常的には次のような方法で自然に水分とミネラルを取りいれるのがおすすめです。
味噌汁やスープを冷やして飲む:塩分とミネラルが自然に摂れます。冷や汁や具沢山味噌汁などがおすすめ。
梅干し入りの麦茶:麦茶はカフェインがなく、体を冷やす作用もあり、梅干しのクエン酸で疲労回復にも。
自家製の塩レモン水や甘酒:ミネラルを補いながら、さっぱりした味で飲みやすく、食欲が落ちたときにも◎。
果物を活用する:スイカやバナナは水分・カリウム・糖分がバランスよく含まれています。
バランスの取れた「夏ごはん」のすすめ
暑さで食欲が落ちると、そうめんや冷たいものばかりになりがちですが、それではエネルギーや栄養が不足し、かえって夏バテを悪化させてしまいます。
食事は、「涼」と「滋養」のバランスが大切です。例えば、冷たいそうめんに薬味やタンパク質(ゆで卵・蒸し鶏・納豆など)を加える、冷しうどんにとろろやオクラを添えるなど、胃腸に優しく、かつ栄養のある食べ方がおすすめです。
また、夏は「心(しん)」の働きが活発にある季節でもあります。心を整えるために、苦味のある野菜や、赤い色の食材(トマト、赤ピーマン、小豆など)を意識的に摂るのも東洋医学的な養生のひとつです。
まとめ
夏は、体に熱がこもりやすく、消耗もしやすい季節。東洋医学の「清熱」「生津」「補気」といった視点と、栄養学の知識を組み合わせることで、心も体も健やかに夏を乗り越えることができます。涼をとりつつ、しっかり栄養も補う「夏の食養生」、ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてください。
著者プロフィール
椙山女学園大学卒業後、食品原料商社にて様々な食品原料の開発に携わる。現在は、フリーランス管理栄養士として年間500人以上に栄養指導、食品添加物セミナー、企業のコラムなどを執筆。また、マクロビ・薬膳・自然療法・望診を学び、西洋・東洋の面から見た、病気にならない体づくりを研究中。
《保有資格》
管理栄養士 / 管理薬膳師 / 上級望診指導士